 |
|
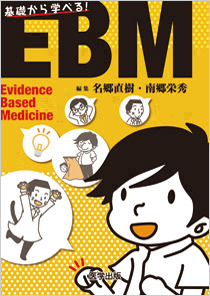 |
|
| 基礎から学べる!EBM |
|
編著:名郷直樹(武蔵国分寺公園クリニック 院長),
南郷栄秀(東京北医療センター 総合診療科 医長) |
|
2014年5月15日発売
A5判●296頁●本文2色刷
価格:本体4,500円+税
ISBNコード:978-4-287-11110-9 |
|
|
|
| 画像をクリックするとサンプルをご覧いただけます |
|
|
|
 |
|
研修医だからこそ,EBMが実践できる。本書はそのお手伝いをします。
研 周囲(けん しゅうい)先生がさまざまな施設で研修するなかで経験する出来事や指導医との対話を読みながら,EBMについて学べる1冊。「月刊レジデント」で連載され大好評を頂いた記事がついに書籍化。
◎多彩なキャラクターたちの対話形式でEBMの基礎から実践,応用まですらすら学べる
◎図や表を豊富に用いることでさらに読みやすく
◎患者さんのための診療を学ぶならこの1冊
|
|
|
|
【はじめに】名郷直樹
●初期研修医がローテート研修する中で,いかにEBMを実践するか?
初期研修医の皆さんにとってEBMの実践は,単なるお題目ではありません。厚生労働省が定める初期研修の行動目標の中にも,問題対応能力の中の一項目として,EBMの実践が明確に掲げられています。つまり,EBMは関心ないから,では済まない,達成されなくてはいけない必須の目標なのです。
私は臨床研修指定病院の教育専任医師として,10年以上にわたって初期研修医のEBM教育に力を注いできました。本書ではそこで培ったノウハウを,もったいぶらずにすべてオープンにして,研修医諸君に臨床現場で,EBMを実践できるような道具立てを提供したい。そしてそれらの道具を使ってもらえるようにしたい,と本気で思っています。
●初期研修中から頭を使おう
研修医は,まず頭より手足が動くことが重要だ。この根強い意見には確かに一理あります。しかし,初期研修のころから頭も使ったほうがいい,という意見にもまた,一理あると思います。頭は使い続けないと,ここぞというときに使えない。初期研修中に使わないと,そのまま一生頭を使わない医師になる危険性もあります。臨床判断を考えずにすることはできません。マニュアル本にしたがって,指導医の言いなりになって,考えずに検査をする。考えずに薬を出す。そんなことをしていると,割を食うのは患者さんたちです。EBMの実践は研修医のためではありません。研修医の皆さんがいま受け持っている患者さん,あるいは将来担当する患者さんのためのものなのです。
研修医だからこそ,EBMが実践できる。私はそう思っています。私自身が,何も知らない研修医であったからこそ,研修が済んだあとも指導医のいないへき地の診療所でどうすればいいかわからない半人前にもならない医師であったからこそ,多少なりともEBMが身についたと思うからです。そこには,いつも体を動かすだけではなくて,考えるということがありました。それでは本題に入っていきましょう。
|
|
|
|
【目次】
1.ステップ0:わからないことをわかる−“わからない”と言えるレジデントになろう−
2.5つのステップとPECO−代用のアウトカムと真のアウトカム−
3.7つのPECO−PECOで定式化できる診断・予後の問題−
4.研修医のための情報源1−診断編−
5.研修医のための情報源2−治療編−
6.研修医のための情報源3−救急外来でのその場の情報収集−
7.研修医のための批判的吟味−批判的吟味の公式−
8.結果の読み方−相対危険,治療必要数,連続変数の評価−
9.危険率と信頼区間
10.仮説演繹法3年C組
11.尤度比・ベイズの定理
12.Clinical Prediction Rule(臨床予測指標)
13.ランダム化比較試験を読む(ITT解析/二重盲検)−3分で論文読めるEBM−
14.ランダム化比較試験を読む(PROBE法)−PROBE法を題材に批判的吟味をする−
15.サブグループ解析とft
16.ボンフェローニ補正
17.メタ分析の論文を使いこなす
18.症例対照研究
19.コホート研究
20.観察研究のメタ分析
21.CONSORT,PRISMA
22.診療ガイドライン−AGREE ⅡとGRADE system−
23.EBMの実践と生涯学習に役に立つサイト「The SPELL」
24.これまでの復習と評価 |