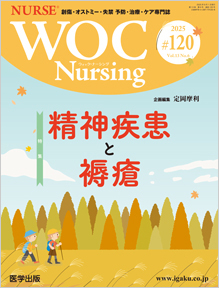
特集●精神疾患と褥瘡
| 企画編集 | :定岡摩利 |
|---|---|
| 発行 | :2025年9月 |
| 判型 | :A4変型 |
| 頁数 | :80 |
| ISBN | :978-4-287-73120-8 |
| 定価 | :2,640円(本体2,400円+税10%) |
特集にあたって
精神科病院では,精神症状と関連して,低栄養になったり,治療に患者の協力が得られなかったりする場合があります。また,ときに必要となる身体拘束や,ほとんどの患者に投与されている向精神薬の影響など,一般病院とは異なる視点での褥瘡対策が必要となります。日本褥瘡学会の現状調査では,国公立の精神科病院が調査対象となっており,褥瘡発生率は一般病院と比較して低い結果となっていますが,精神科病院の約9割を占める民間施設の現状が反映されているわけではありません。また,日本精神科看護協会が作成している「精神科病院における障害者虐待防止の手引き」のなかには,放棄・放置(ネグレクト)の例として褥瘡が挙げられており,精神科病院の抱える大きな問題として取り上げられていることからも,精神科病院での褥瘡対策の特徴を把握し,ポイントを整理する必要があると思います。
実際の臨床現場では,最も患者と接している看護師の視点が重要であり,患者個々の精神症状や日常動作の特徴を踏まえた介入が望まれます。向精神薬は薬剤関連褥瘡として,薬剤を起因として発生する褥瘡につながり,令和2(2020)年の診療報酬改定では薬学的管理を行うこととなりましたが,精神科病院においては必要とされる患者に投与されるものであり,適正使用の視点から薬剤師の介入が重要です。また,身体拘束などの行動制限は患者の動きを抑制することから褥瘡発生の要因となる場合があり,マットレスの使用が困難となる場合もあります。これら身体機能への働きかけとして理学療法士や作業療法士の視点が重要となり,これらすべての職種の介入において精神科治療が中心であることが重要です。
精神科病院では,その歴史的背景から「精神科特例」として,医師は他の病床の3分の1,看護師は3分の2という配置基準の規定がありました。平成13(2001)年に廃止されたものの,多くの精神科病院での基準は変わることなく,少ない医療従事者で,医療安全,院内感染,褥瘡対策などそれぞれの分野で一般病院と同様の施設基準が求められている現状があり,患者1人にかかわることのできる医療従事者の数が少なく,時に相反する精神科治療と褥瘡ケアを両立するためにも,より多職種による専門的な介入や連携は不可欠です。また厚生労働省は,精神障害の有無や程度にかかわらず,誰もが安心して自分らしく暮らすことができるよう,医療,障害福祉・介護,住まい,社会参加(就労など),地域の助け合い,普及啓発(教育など)が包括的に確保された「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を進めており,今後は精神疾患患者においても医療機関と在宅での褥瘡ケアの連携が,より一層重要になります。
本特集では「精神疾患と褥瘡」をテーマに精神疾患に対する理解を深め,精神科治療や精神症状を踏まえ,多職種の視点での褥瘡予防・治療,さらには医療機関と在宅医療での褥瘡ケアの連携など,それぞれの現状と課題を多くの先生方にご執筆いただきました。精神疾患患者の褥瘡ケアの一助になれば幸いです。
目次
Part1 精神疾患の病態と向精神薬